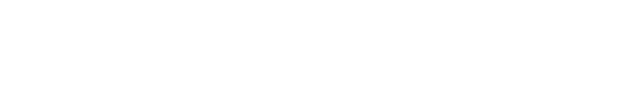余韻
診療が終わったのは、14時を少し過ぎたころだった。
西公園で桜祭りをやっている。そんな話を昼に耳にした。
なんとなく屋台くらいはあるんじゃないかと期待して、終わってすぐに家族を呼んで、歩いて向かうことにした。
公園までは歩いて5分。
桜は、ちょうど満開だった。
空に向かって広がる枝が、花で膨らんで、風にふわっと揺れている。
陽ざしに照らされた花びらが、どこか舞台の照明みたいで、「まだ何かが続いている」ような気さえした。
でも、公園の中央にあったはずのステージには、もう誰もいなかった。
ロープが巻かれ、看板が片づけられ、露店の痕跡すら見当たらなかった。
あぁ、もう終わっていたのか。14時すぎには終わっていたらしい。
祭りに来たつもりが、すでに祭りは過去だった。
それでも、桜は咲いていた。
満開の桜には、終わりも始まりもない。
ただ咲いて、散る準備をしているだけだった。
子どもたちは、祭りの終わりなんて気にしていなかった。
「じゃあ、鬼ごっこしよう!」と長男が叫び、もう祭りの記憶はこどもたちの頭から消えていた。
全力で走って、転んで、笑って、また走っていた。
それに付き合った僕は、5分で息が切れた。
マラソン勝負まで始まり、もう何のイベントだったのかわからない。
それでも楽しかった。桜の下で全力で遊ぶというのは、想像以上に春らしい行為だった。
帰り道、長男と次女が「帰りたくない」と言った。足はまだ動いていて、目は爛々としていた。
こっちは足が棒で、肩も重い。
でも、そう言ってもらえる春の午後が、なんだかうれしかった。
花見だったはずが、ただの全力運動になっていたけれど、でも、あの満開の桜の下で、何かが確かに残っていた。
人の気配も、音楽も、甘い匂いも、もうない。
でも、あの場所にまだ「祭りのかけら」が、ほんの少し漂っていた気がした。
それが春の「余韻」というものなのかもしれない。
それは桜の色でも、屋台の名残でもない。
もう片づけられたステージのすぐそばで、鬼ごっこをしていた僕たちの息づかいのようなものだった。
春は、少し遅れて来る人にも、ちゃんと優しい。