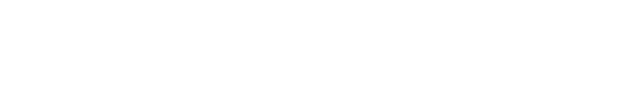釣りバカ日誌 〜海がまだ、よそよそしい。
今朝は、誰よりも早く目覚めた……わけではなかった。
正直に言えば、目覚ましが鳴るより先に、長男の「起きて!釣り行くよ!」という声で叩き起こされた。まだ薄暗い部屋の中、長男の声だけがやけに透き通っていた。普段はどちらかというと寝坊助なはずが、今日はなぜか家族の誰よりも早く動いていた。母親にタックルボックスの場所を聞いたり、妹たちの防寒具を用意したり、「早くしてよ!」と、小さな船長のようにせっせと家族に声をかけていた。
そんな息子に促されるまま、僕らは沼津港へと車を走らせた。到着した港には、ゆるく冷えた朝の風と、潮の香りが混ざっていた。
海釣りはまだ2回目。道具の持ち方にも、海の広さにもまだ慣れていない。あらかじめ魚を放流される釣り堀ではない、無限大の海を前に僕は、釣れるかどうかがずっと不安だった。
そんな不安を胸にしまいながら、海をにらむように見つめ、潮の香りを吸い込んだ。
結果としての釣果は、コサバ3匹とカサゴ1匹。そのうち3匹を釣ったのは、小学一年生の次女。
サビキ仕掛けを垂らしては、黙々と海面をのぞき込む彼女の姿は、驚くほど落ち着いていた。「来た」とも言わず、音もなく、確かに魚を引き上げていった。
釣れた魚を見て、長男が「これ、小さくても食べられる?」と聞いたとき、妻がスマホを取り出して、アプリで魚を判別し、料理方法まで調べていた。「うん、唐揚げがいいみたい」と、早々に献立まで決まっていった。
魚はどれも小ぶりで、包丁を入れるようなサイズではなかった。丸ごと、粉をまぶして、油の中に泳がせた。音を立てながら揚がっていく魚たちは、ついさっきまで海の中で泳いでいたとは思えないほど、カリッと香ばしかった。
じゅうじゅうという音の向こうで、子どもたちは自分が釣った魚の所在を確認しあっていた。
「これ、わたしが釣ったのかも」
「いや、たぶん、あれはおれが釣ったコサバだよ」
僕はどれでもいいと思った。
唐揚げになってしまえば、どれが誰の魚かなんて、少なくとも僕には、もうわからない。
魚がどれであっても、その時間が、確かに今日という一日を釣り上げていた。
揚げたての魚を頬張りながら、少しだけ、あの海に礼を言いたくなった。
不安を隠したままの父親の手元にも、今日という日がちゃんと残った気がした。
また行きたい。釣れるかどうかという僕の不安なんて、海は知ったことじゃない顔をして、また黙って待っているに違いない。